ご挨拶
令和7年9月1日付けで、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部の部長を拝命いたしました髙橋長秀と申します。
私は小学生の頃から、自分は何となく人と違う気がする、という感覚を持ちながら生きて参りました。やたら細かいことにこだわってしまったり(道を歩いていると、左にあるマンホールと右にあるマンホールの数が同じでないと気が済まない)、やたら匂いに敏感ですぐに乗り物酔いしてしまったり、そうかと言うと、不注意ですぐに物を壊したり、怪我が多く何回も車に轢かれたり、ということもありました。
名古屋大学の医学部の授業で「発達障害」という言葉を知り、精神科に進み、多くの患者さんと接するうちに、自分が感じていた違和感にはもう既に固有名詞があり、その違和感は自分だけのものではないんだ、と言うことが分かって来ました。
その後、名古屋大学大学院に入学し、当時の尾崎紀夫教授、稲田俊也准教授から遺伝子研究の基礎を学び、ニューヨークのマウントサイナイ医科大学ではJoseph Buxbaum、Takeshi Sakurai両教授の元で、念願の神経発達症の分子生物学的研究を行い、帰国後は浜松医科大学の土屋賢治先生の神経発達症に特化したコホート研究のチームに参加させて頂き、Yoko Nomura先生からも疫学研究の重要性を学びました。
また、その間には、製薬会社で神経発達症の新薬の開発と承認に関わることができました。
さらに、父親の急逝に伴い継承したクリニック、浜松市の単科精神科病院である朝山病院、名古屋大学医学部附属病院と、様々な環境で沢山の神経発達症の当事者とその支援者の皆様から、励まされ、学ばせて頂きながら、臨床に従事して参りました。
このように、かなり異色の経歴を有する私が、この歴史と伝統のある、また現在、社会的にも大変重要性を増している知的・発達障害研究部の部長という責務を果たせるか、大変な重圧を感じずにはいられませんが、優秀なスタッフ、恵まれた研究環境を十二分に活かして、当事者、支援者の皆様に還元できる成果を上げて参りたいと思います。
さて、この「ご挨拶」は、新幹線の待合室で書いているのですが、どうやら、予約していた新幹線は先程、もう発車してしまったようです。まあ、こんなことは日常茶飯事なのですが、一応ガッカリします。
話が逸れてしまいました。
結局はご縁がなかったのですが、あるポジションに応募した時に、選考委員の先生から「君は色々なことがあって、色々なことをやってきたのに、ずっと研究に対する情熱を失わずにやって来た。そのことが本当に素晴らしい」と勿体ないお言葉を頂きました。自分では、行き当たりばったりの人生を歩んで来たような気がするのですが、おそらく、小学生の頃に読んだ手塚治虫の「ブッダ」の「人は生まれて来たからには何らかの役割を持っているんだよ」というセリフが心のどこかにいつもあって、節目節目に「これが自分の今やるべきことなのかも知れない」と思って生きて来た結果が、その先生には何か筋の通った生き方と見えたのかもしれません(ちなみに私は仏教徒というわけではなく、富士山の見えるところに住んでいるので、富士山を信仰しており、「いつか宝くじが当たりますように」と富士山にお祈りをしています)。
ただ、それに振り回される家族は堪ったものではないと思いますので、この場を借りて、深くお詫びしたいと思います。これからは、物も出しっ放しにしないようにします。ちゃんと電気も消します。ゴミもゴミ箱に捨てるように心掛けます。
これまで、私を支えて下さった皆様に心から御礼を申し上げるとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。乱筆乱文ではございますが、これにて、ご挨拶に代えさせて頂きたいと思います。
敬具
髙橋長秀
国立精神・神経医療研究センター 知的・発達障害研究部 部長
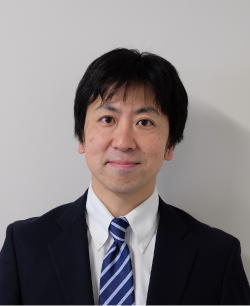
知的・発達障害研究部
部長 髙橋長秀