
脳神経内科コース
- TOP
- 採用情報
- レジデント・臨床研修
- 脳神経内科コース
プログラムの目的と特徴
脳神経内科専門医に求められる知識と技術を修得し、独立して専門医療を行うことが到達目標である。日本神経学会認定教育施設として、日本神経学会の定めたガイドラインに沿った研修を行い、脳神経内科専門医として必要な診断・検査・治療・生活指導などの知識と技術を習得する。
脳神経内科の病床数は約130床であり、3つの病棟に分かれている。3病棟をまんべんなくローテーションすることでバランスの取れた研修を行う。各病棟には病棟医長を中心に5〜6名の指導医が配置され、各々の専門性を活かした熱意ある指導を行っている。さらに、院内での各種セミナー・研修会など教育機会がふんだんに提供されることも当院のプログラムの特徴である。また、夜間・休日は原則として当直医が対応するため、ワークライフバランスの取れた研修が可能である。
当科では希少疾患からcommon diseaseまで、脳血管障害急性期を除くすべての領域を網羅した症例経験を積むことができる。とくに神経変性疾患(パーキンソン病・脊髄小脳変性症・筋萎縮性側索硬化症など)、免疫性神経疾患(多発性硬化症・視神経脊髄炎・慢性炎症性脱髄性多発神経炎など)、筋疾患(筋ジストロフィー・筋炎など)、認知症(アルツハイマー型認知症、レヴィ小体型認知症、前頭側頭型認知症など)を中心に多種多様な症例を経験する。年間入院患者数延べ3000名以上と、神経筋難病に特化した診療部門としては国内でも圧倒的な質量を誇る。発症早期例の入院評価も積極的に行っており、臨床診断、検査、治療、生活指導までを包括的に研修することが可能である。他院での診断困難例・治療難渋例の紹介入院も多く、当院ならではの診断・治療プロセスに触れることができる。
さらに、神経・精神疾患の高度専門医療施設である当院の特徴をいかし、精神科、脳神経外科、脳神経小児科、身体リハビリテーション科、整形外科等と連携して診療を行う。移行医療についても学ぶ機会が多い。
なお、内科研修制度の改変に伴い、当院は連携施設として後期研修教育に携わる。すなわち、それぞれの基幹施設の内科研修プログラムの中の脳神経内科分野を担当することになる。各施設のプログラムに対応した柔軟な研修期間の設定も可能であり、不明の点は個別に担当まで問い合わせていただきたい。後期研修3年目で当院での研修を行った場合、そのままシニアレジデントへと移行して研修を継続することも可能である。
上級専門修練医制度
日本神経学会の専門医資格取得後、「上級専門修練医」として、脳神経内科のなかでもサブスペシャリテイーを追求し、臨床研究も含めたより専門的な研修を行うコースである。自らの専門性を探究し、将来の方向性を確立する為の、有意義なプログラムである。
当科スタッフはそれぞれの専門分野でも理事・代議員・評議員等指導的な立場にあり、当院は認知症、てんかん、臨床神経生理、神経病理、臨床遺伝など多数の専門学会の教育施設に認定されている。したがって希望するサブスペシャリティと関連した専門学会での研修や、それぞれの専門医・認定医を取得するために必要なカリキュラムは整備されており、必要に応じた年限の研修が可能となっている。
連携大学院
入学試験を受験後、一定のカリキュラムの履修により、提携を結んでいる東京大学、東京科学大学、千葉大学、東北大学、東京慈恵会医科大学、信州大学等の医学系大学院博士号取得が可能である。社会人大学院の制度も整備されており、診療を行いながら臨床研究を行い学位を取得することができる。
研修内容と到達目標
以下の日本神経学会の卒後研修到達目標に準拠する。
(1)診察
脳神経内科の診断で最も重要な問診と神経学的診察法を学ぶ。問診と診察により診断を組み立てる過程を身につける。画像検査や遺伝子検査の発達した現在もやはり、自分の五感を使い、患者さんから最大限の情報を引き出すことが基本である。新しい疾患概念の確立や新しい治療法の発見も、しばしばベッドサイドでの着想が発端である。
(2)検査
研修到達目標にあるように針筋電図、神経伝導速度、脳波などの神経生理検査については1人で検査ができ、かつ結果の判定ができるようにする。研修プログラムのうち、病棟主治医期間は受け持ち患者さんについて指導医の指導下で検査を実施する。日本神経生理学会の教育施設であり、認定医取得も可能である。
神経筋病理については指導医のもと、一人で神経・筋生検、および標本作成、基本的な染色を行い、適切な結果の解釈ができるようにする。またCPCを担当する。当院臨床検査部、神経研究所疾病研究第一部には10,000例をこえる筋疾患バンクがあり、年間700例をこえる検体の診断を行っているので、神経筋病理専修期間中はこのバンクを生かして研修する。
MRI、CT、SPECT、PETなど最先端の装置を用いた神経放射線学的検査を行い、放射線部の協力のもと画像検査の判読及び解釈に習熟する。
当院では院内および他施設と連携して積極的に遺伝子検査を行っており、病因診断を徹底的に行って診療に活用している。確定した病因に立脚した臨床経験は一般化が可能であり、脳神経内科医としての経験値を高めることに大きく貢献する。
(3)治療
ガイドラインを遵守した標準的な治療を実践すると共に、医師主導治験を含めた多くの先端医療に参加する。パーキンソン病については薬物コントロールに加え、脳深部刺激療法(DBS)・Lドパ持続経腸療法・Lドパ持続皮下注射法などのDevice Aided Therapy(DAT)についても実践的に学ぶ。免疫性神経疾患については、最新の疾患修飾治療の導入から維持療法まで多数の症例を経験できる。筋疾患は酵素補充療法・エキソンスキッピング等の疾患修飾療法の実例を経験するとともに、呼吸・循環管理をはじめとする全身管理を学ぶ。認知症については一般的な維持管理療法に加え、病態修飾治療(レカネマブ・ドナネマブ)の実施経験も積む。そのほか、脊髄性筋萎縮症、ATTRvアミロイドーシス、SOD1陽性家族性筋萎縮性側索硬化症など、遺伝性神経疾患に対する核酸医薬の実施例も多い。ジストニアについても多数の症例に対して、内服薬・ボツリヌス治療・外科治療を組み合わせた治療法を学ぶ。
神経疾患全般に関して、他部門との連携により総合的な治療を行うことも特色である。精神科との連携により抗精神病薬や抗うつ薬の使用経験を積む。整形外科との連携により、痙縮に対するバクロフェン髄注療法、疼痛に対する脊髄電気刺激療法などの実施例を経験する、身体リハビリテーション部との連携により神経リハビリテーションの基本的な考え方と実践について学ぶ。ソーシャルワーカーなどとの多職種連携により、患者さんおよびご家族への生活指導・環境調整・社会的支援についても学ぶ。特に神経筋難病に対する支援制度に通暁することは、患者さんや家族のQOLを維持する上でも非常に重要である。
(4)遺伝カウンセリング
神経疾患は遺伝性疾患も多く、遺伝子検査の理解と実践は必須である。当院は日本人類遺伝学会の認定を受けた教育施設であるので、3年間の教育により臨床遺伝専門医受験資格を得ることが可能である。遺伝カンファレンスに出席し遺伝カウンセリングの実際について研修する。
(5)研究
研究推進は当センターの使命の一つである。豊富な症例に基づく臨床研究と、バイオバンク等臨床試料を活用した基礎研究の両立・融合が当科の特色である。研究所と連携した疾患研究も数多く推進されている。さらに、未診断疾患イニシアチブIRUD、筋ジストロフィー患者レジストリRemudy、運動失調症の患者登録・遺伝子解析・自然歴研究J-CAT、プリオン病自然歴研究コンソーシアムJACOP、パーキンソン病の発症早期バイオマーカー探索研究J-PPMIなど、当センターが中心のオールジャパンの多施設共同研究に関わる機会も準備されている。
研修中に症例報告も含め2本の論文を書くことを目標にしている。2024年度に当科のレジデントが執筆し発表した英文論文数は7編である。また研修の一環として、全員、毎年日本神経学会総会で発表することが基本である。2-3年目には研究プロジェクトに参加したり、研修中に得た着想に基づいた臨床研究を立案し、データを収集して結論を導き出す訓練をする。当センター内で企画される多くのセミナーに参加して、実際に研究を進めるための具体的なノウハウを学ぶ。
(6)専門疾病センター
国立精神・神経医療研究センターでは、12の専門疾病センターがあり、各診療部や、検査部、看護部のみならず、同じキャンパス内の神経研究所、精神保健研究所とも連携し、高度専門的医療、診断・治療法開発を行っている。なかでもパーキンソン病・運動障害疾患センター、多発性硬化症センター、筋疾患センター、てんかんセンター、認知症センター、嚥下障害リサーチセンターにおいては脳神経内科が中心的な役割を果たしている。それぞれのセンターは専門外来や、月1回程度のセミナーなども開催している。レジデントはこれらに参加することにより、専門分野の研修を深めることができる。
<脳神経内科レジデントの週間スケジュール>
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |||
| 08:00 |
チャート ラウンド |
||||||
| 08:30 | 病棟 | 病棟 |
電気生理 検査 |
多発性硬化症 カンファレンス |
|||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 |
病棟 |
||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
お昼 |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | 病棟 | 病棟 |
医局会 | 病棟 | 病棟 |
||
| 13:30 |
ボトックス・ ゼオマイン 注射研修 |
||||||
| 14:00 | 病棟回診 |
嚥下造影 検査 |
|||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
てんかん手術症例カンファレンス |
てんかん症例カンファレンス |
てんかん 手術症例 カンファ |
||||
| 16:30 |
嚥下web カンファ |
||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | 遺伝勉強会 |
|
|||||
| 18:00 | |||||||
上記以外のカンファレンス
第4月曜 17:00~17:30 DBSカンファレンス
月1回程度 火曜 12:00~13:00 CPC
月1回程度 金曜 8:00~9:00 CMC(筋疾患カンファレンス)
月1回程度 金曜 12:00~13:00 遺伝カウンセリングカンファレンス
月1回程度 金曜 15:00~16:30 筋病理カンファレンス
週間スケジュール
毎週水曜日にチャートラウンドと病棟回診が行われる。レジデントは担当の患者をプレゼンし、科内でディスカッションして方針を決定する。また別日に、各病棟において病棟医長回診が行われる。回診に出席することにより、担当以外の患者についても学び、臨床経験の幅を拡げることが可能である。また水曜日は脳神経内科医局会、抄読会、CC(Clinical conference)も併せて開催される。月一回はスタッフの研究紹介が行われ、当センターでの現在進行形の研究の一端に触れることができる。
合同カンファレンスとして、脳神経外科・内科合同カンファ、てんかん症例カンファ(脳神経外科、脳神経小児科、精神科)、身体リハビリテーションカンファ、筋疾患カンファ(脳神経小児科)、姿勢異常カンファ(リハビリ科)、遺伝カンファ(遺伝カウンセリング室)、神経研究所での筋病理カンファ、などがある。また科内でもMSカンファ、嚥下カンファなど多岐にわたるカンファレンスがあり、専門的な知見を得て臨床に還元することが可能である。
参 考 日本神経学会 神経内科卒後研修到達目標 臨床神経 1998:38:593-619
指導医リスト

水澤 英洋
役職
理事長特任補佐
名誉理事長
経歴
東京大医 昭和51年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定医・指導医
日本脳卒中学会専門医・指導医
日本認知症学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本神経学会元代表理事
日本神経感染症学会元理事長
日本神経病理学会前理事
全国大学医師会連絡協議会顧問
東京医科歯科大学大学院
特命教授・名誉教授
日本医師会認定産業医
戸田 達史
役職
病院長
経歴
東京大医 昭和60年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医、指導医、理事
日本内科学会認定内科医
日本人類遺伝学臨床遺伝専門医、理事
日本神経学会元代表理事
東京大学大学院名誉教授

高橋 祐二
役職
特命副院長
脳神経内科診療部長
ゲノム診療部長
経歴
東京大医 平成6年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医・理事
日本内科学会総合内科専門医
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医・評議員
日本頭痛学会専門医・教育関連委員・評議員
東北大学客員教授
信州大学客員教授
東京慈恵会医科大学客員教授
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診断ガイドライン2018作成委員
頭痛の診療ガイドライン2021作成委員
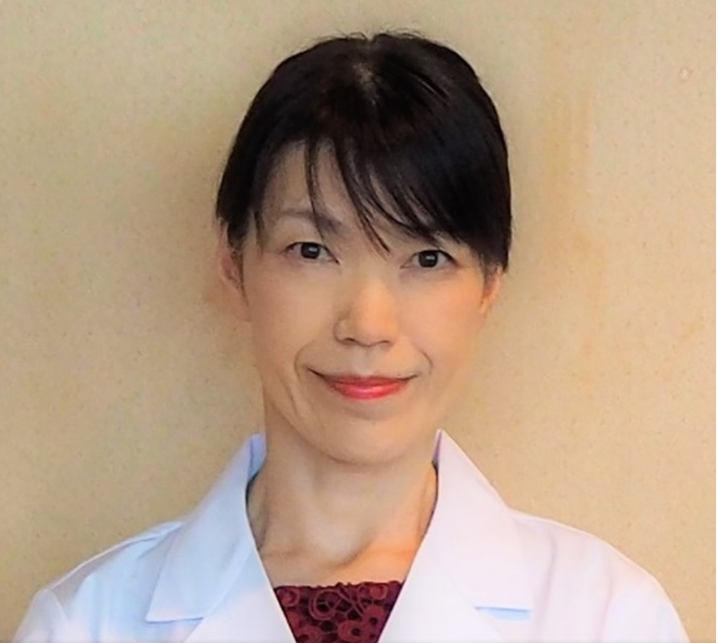
岡本 智子
役職
脳神経内科副部長
経歴
滋賀医大 平成元年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医・代議員
日本内科学会認定医
日本臨床免疫学会免疫療法認定医
日本末梢神経学会評議員
日本神経免疫学会神経免疫診療認定医・評議員
多発性硬化症/視神経脊髄炎診療ガイドライン作成委員
日本神経学会母性神経学セクションコアメンバー
大矢 寧
役職
脳神経内科医長
経歴
東京大医 昭和62年卒
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
リハビリテーション医学会臨床認定医
日本神経病理学会評議員

坂本 崇
役職
脳神経内科医長
経歴
京都大医 平成6年卒
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定医
日本神経生理学会認定医・指導医・
神経超音波研究会世話人
ボツリヌス療法研究会評議員
徳島大学神経内科臨床教授
ジストニア診療ガイドライン作成委員
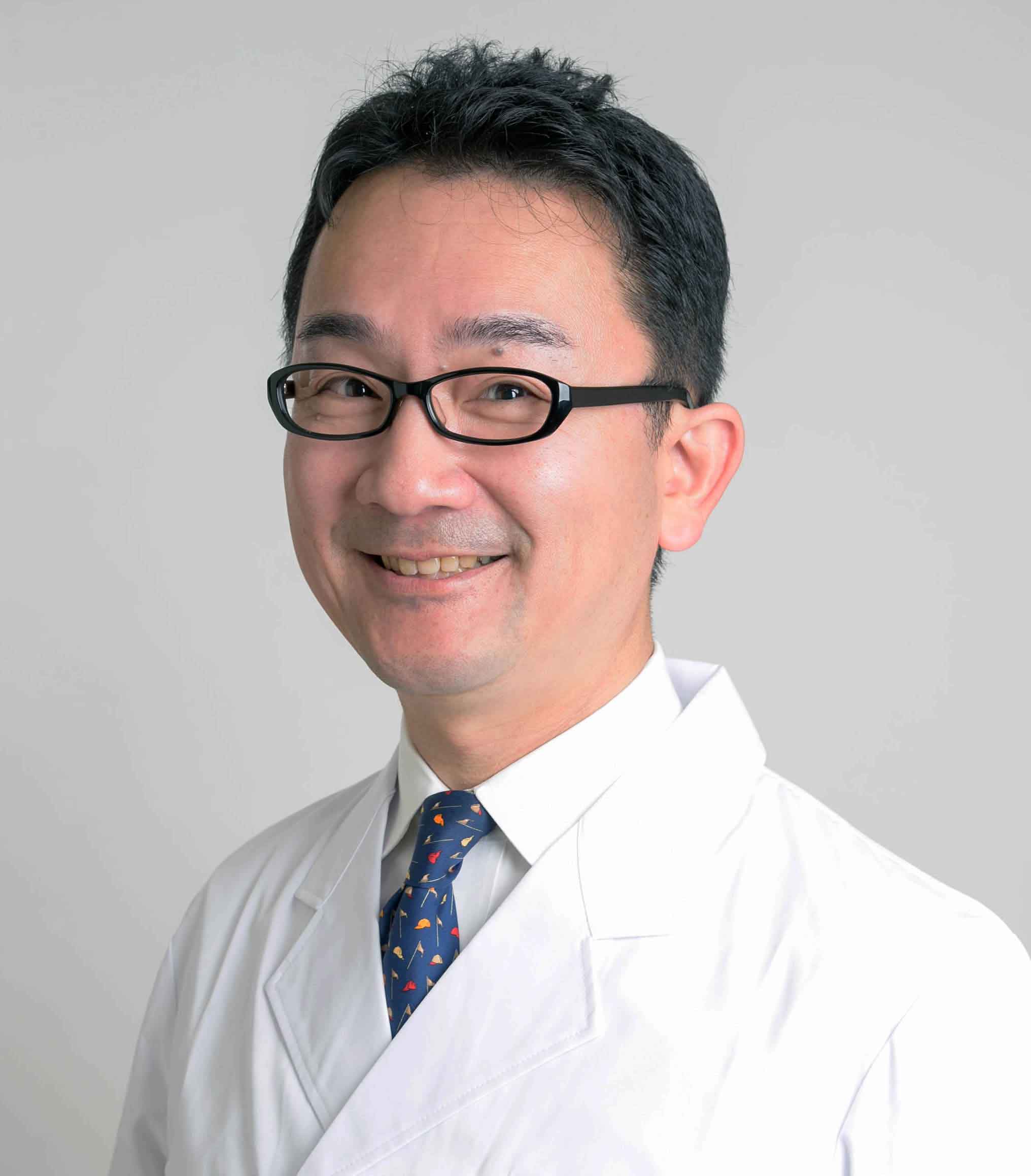
山本 敏之
役職
脳神経内科医長
経歴
札幌医大 平成8年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定医・指導医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会学会誌編集委員
日本嚥下医学会評議員
藤田医科大学医学部客員講師
パーキンソン病診療ガイドライン作成委員
嚥下障害診療ガイドライン作成委員
デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドライン委員
進行性核上性麻痺診療ガイドライン作成委員
筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン作成委員

弓削田 晃弘
役職
脳神経内科医長
経歴
金沢大医 平成13年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定内科医
日本定位・機能神経外科学会技術認定医
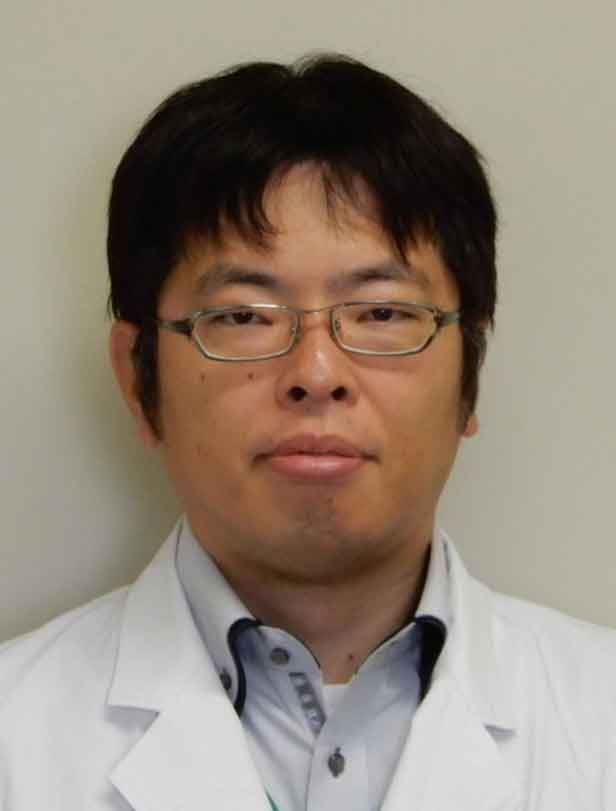
向井 洋平
役職
脳神経内科医長
経歴
徳島大医 平成15年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医

勝元 敦子
役職
脳神経内科医長
経歴
宮崎大医 平成17年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本認知症学会専門医・指導医

林 幼偉
役職
脳神経内科医師
経歴
京都大医 平成8年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定医
日本神経免疫学会評議員
日本アフェレーシス学会認定専門医・評議員
アフェレーシス診療ガイドライン作成委員

金澤 恭子
役職
脳神経内科医師
経歴
琉球大医 平成16年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本臨床神経生理学会専門医
(脳波、筋電図・神経伝導)・指導医
日本てんかん学会専門医・指導医・評議員
・医療費問題検討委員・選挙委員
日本てんかん学会関東甲信越地方会評議員
日本神経学会てんかんセクションコアメンバー
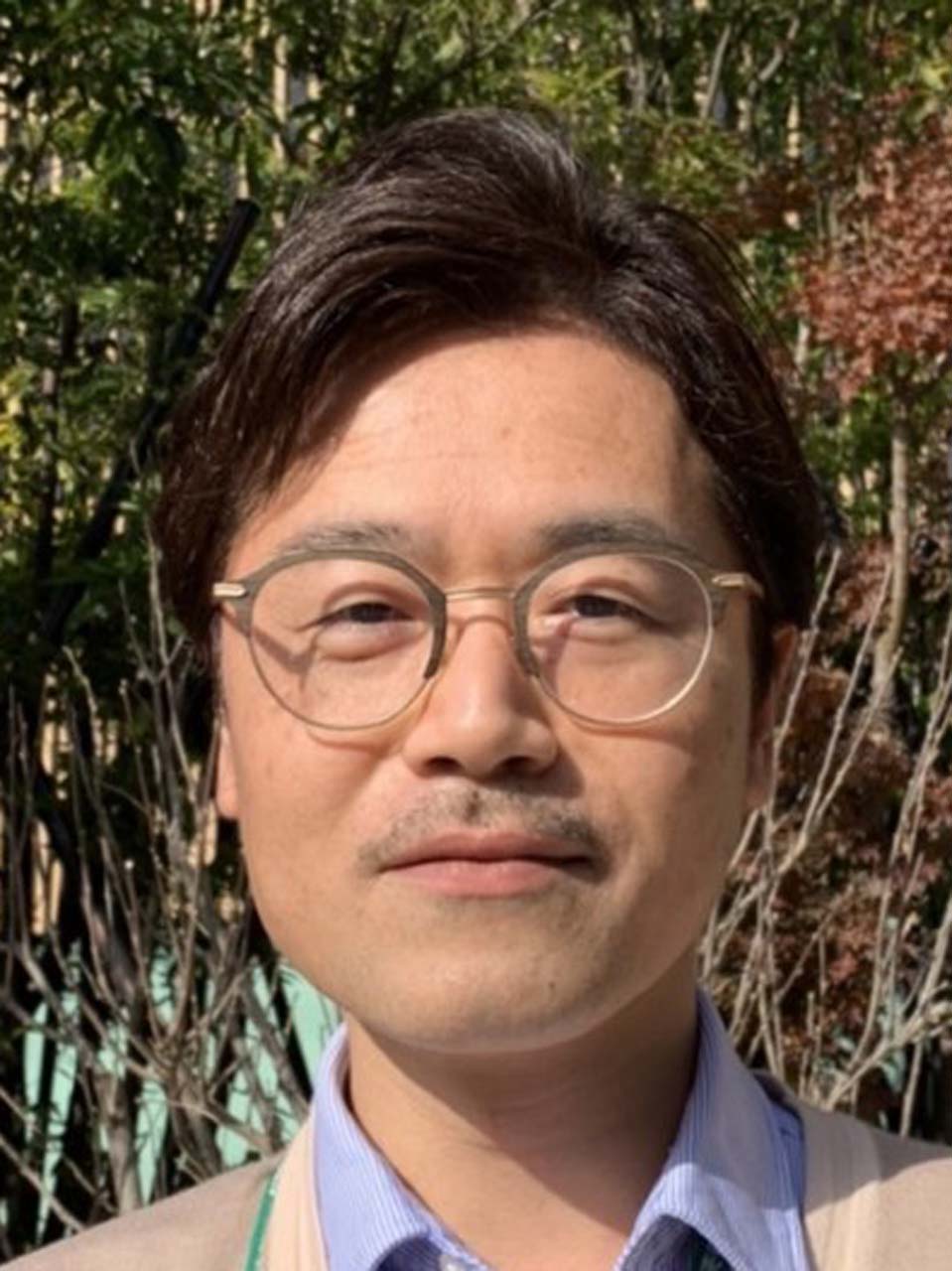
滝澤 歩武
役職
脳神経内科医師
経歴
鳥取大医 平成17年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本リハビリテーション医学会専門医

雑賀 玲子
役職
脳神経内科医師
経歴
島根大医 平成18年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本認知症学会専門医

中元 ふみ子
役職
脳神経内科医師
経歴
日本大医 平成20年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
佐藤 奈穂子
役職
脳神経内科医師
経歴
東京女子医大 平成20年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

常山 篤子
役職
脳神経内科医師
経歴
千葉大医 平成22年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本臨床神経生理学会専門医
(筋電図・神経伝導分野)

鵜沼 敦
役職
脳神経内科医師
経歴
滋賀医大 平成23年卒 医学博士
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会総合内科専門医
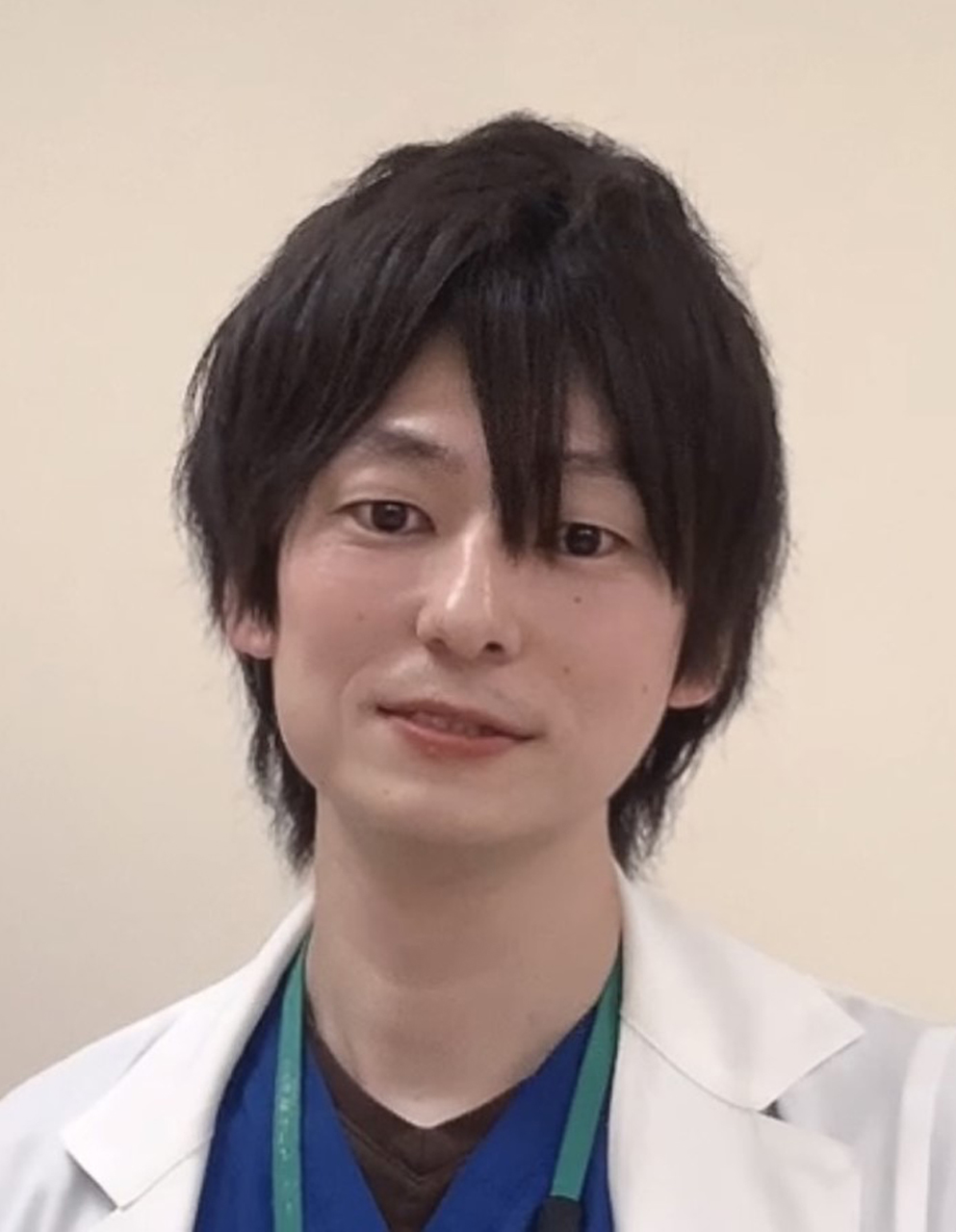
小田 真司
役職
脳神経内科医師
経歴
広島大医 平成24年卒
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会認定内科医
石原 資
役職
脳神経内科医師
経歴
東北大医 平成26年卒
専門分野・資格
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会認定内科医


