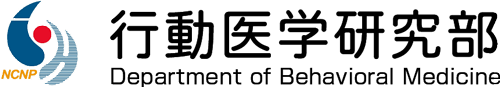複雑性PTSDに関する治療法と診断評価尺度の検証
複雑性PTSDに対する認知行動療法である,STAIR Narrative Therapyの日本での指導者および治療者育成を進め,無作為化比較試験の準備を進めた.また日本語版の国際トラウマ面接(ITI)および国際トラウマ質問票(ITQ)の妥当性研究を進め,現在までに88例のデータを収集し継続中.(金,丹羽,成田恵,中野,島津,蔵下,遠藤,堀)
PTSDの病態解明と治療効果予測法開発に向けた,遺伝子・バイオマーカー・心理臨床指標による多層的検討
トラウマ体験者(PTSD群,非発症群)と健常者を対象とし,遺伝子解析・発現解析,内分泌・免疫系マーカー測定,自律神経機能解析,脳MRI計測,認知機能測定,心理・臨床評価を行い,PTSDの病因病態解明,客観的治療効果予測法の開発を目指す.現在までに364名のデータを収集し継続中.本年度はPTSDにおける脂肪酸プロファイルを明らかにした論文をProgress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry誌に発表した.(堀,伊藤,林,丹羽,金,成田恵,河西,井野,吉田,中野,島津,遠藤,蔵下,小川)
PTSDに対するメマンチンの有効性に関する臨床試験
PTSD患者において,抗認知症薬メマンチンの有効性を検討する.初めにオープン臨床試験を行い,すでに目標症例数である計20名を組み入れ,データ収集を完了した.顕著な症状改善効果が得られ,忍容性も良好であった.この結果を受けて現在,PTSDに対するメマンチンの有効性と安全性を検証するRCTを実施しており,また,RCTを完了した被験者を対象としたメマンチン長期オープン試験を実施している.並行して,メマンチン治療前後で遺伝子発現解析や内分泌・免疫系測定,脳MRI計測を行い,治療効果機序の解明および治療効果サロゲートマーカーの開発を目指す.(堀,小川,井野,成田瑞,伊藤,成田恵,中野,島津,遠藤,蔵下,金)
PTSDに対するメマンチンの有効性及び安全性を評価する無作為化二重盲検プラセボ対照比較試験
PTSDに対するメマンチンの有効性を実証するため,中等症以上のPTSD患者40例を目標として無作為化二重盲検プラセボ対照比較試験を実施している(特定臨床研究:CR21-005).服用開始から13週後のPTSD症状に対する改善効果を主要評価項目とし,副次評価項目も併せてプラセボに対する実薬の優越性を検討する.R6年度は16例の同意を得,14例の患者を組入れ,対象者リクルートを継続中.(堀,小川,井野,成田瑞,藤内,丹羽,成田恵,中野,島津,蔵下,遠藤,金)
血液検査による統合失調症・気分障害の診断法の開発に関する研究
患者・健常者から血液を採取し,タンパク・mRNA・代謝物などを定量し,統合失調症や気分障害の診断法や分類,経過判定指標に役立つ分子の同定を目的とする.神経研究所疾病研究第三部との共同研究として実施し,すでに約3,000名の被験者のサンプルが集積されている.これらの血液サンプルを用いて上記の測定を行い,精神疾患のバイオマーカー候補を探索している.(堀,小川,吉田)
ヒト毛髪を用いた精神疾患バイオマーカーの探索
気分障害,精神病性障害,PTSD等の精神疾患を対象として,毛髪中のステロイドホルモンなどの濃度を測定し,バイオマーカーの同定を目的とする.神経研究所疾病研究第三部,センター病院,MGCバイオリソース部との共同研究として実施しており,被験者リクルート中である.(堀,吉田,蔵下,石渡,土嶺)
情報処理バイアスを標的とした心理治療の有効性の検証とその神経生物学的機序の解明
ストレス関連精神障害に対するリスク保有者を対象として,記憶領域にも働きかける新しいCBMの有効性およびその神経作用機序について,北里大学,労働安全総合研究所等と共同で,fMRIや遺伝子,内分泌・免疫炎症系指標を用いて包括的な観点から検証している.本年度はPsychoneuroendocrinology誌に論文を発表した.(袴田,堀)
摂食障害支援拠点病院における相談・支援事例の調査
摂食障害支援拠点病院での相談・支援事例を収集,集積し,内容を解析し,摂食障害の支援体制モデルの確立に資するための研究を実施した.令和6年度は,全国を対象とした相談「ほっとライン」と8カ所の支援拠点病院の相談事例を報告書にまとめる.(井上,井野,関口)
摂食障害支援拠点病院における摂食障害入院データの調査・解析
摂食障害支援拠点病院での入院事例を収集,集積し,内容を解析し,摂食障害の診療連携モデルの確立に資するための研究を開始した.R6年度より8拠点病院にてデータ収集を開始した(井上,井野,関口)
神経性過食症に対する認知行動療法の無作為比較試験
日本人の神経性過食症患者を対象に摂食障害の認知行動療法「改良版」(enhanced cognitive behavior therapy : CBT-E)の効果検証のため,東京大学,東北大学,九州大学,国立国際医療研究センター国府台病院,および当センターTMCとの多施設共同無作為化比較試験を実施している.NCNPにおいてはすでに登録は終了し,協力施設においてもデータ収集が完了した.現在,データ固定の作業も完了し,解析を実施している.(小川,小原,関口,船場,成田恵,中野,富田,安藤)
摂食障害に対する認知行動療法の有効性の神経科学的エビデンスの創出
摂食障害への認知行動療法(CBT)前後の縦断的観察研究を実施し,CBT前後の脳MRI,臨床データ,遺伝子発現データを収集し,CBT効果の神経科学的エビデンスを創出することを目指す.本研究成果として,Molecular psychiatry誌,Psychological medicine誌に論文を出版し,Neuroimage Clinical誌に論文が受理され,電子版が出版されている.(関口,井野,小川,安藤,堀,勝沼,髙村,成田恵,中野,船場,小原,守口,冨田)
病院 気分障害センターおよびバイオバンクとの共同研究
NCNP病院・気分障害センターおよびNCNPバイオバンクと連携した共同研究課題を実施している.うつ病など多くの精神疾患の発症リスクは幼少期トラウマ(小児期逆境体験)の経験率に伴い上昇することが報告されているが,本課題ではこれまで気分障害センター外来を受診し,バイオバンクでの研究参加登録を頂いた方々の試料と情報を対象として,小児期逆境体験とうつ病など精神症状の発現とに関連する生物学的マーカーの探索を目的として解析を進めている.(小川,堀,金)
病院 脳神経内科診療部との共同研究
NCNP病院 脳神経内科診療部における「中枢神経系炎症性脱髄疾患の患者」を対象に,精神症状・高次機能障害を評価し,その特徴とリスク因子の関連性について「小児期逆境体験」やQOLに着目しながら広く解析することで,脳神経内科および精神科領域において将来的な医療・研究につなげるためのデータを探索的に収集している.R6年度は論文化作業を進めた.(小川,堀,金)
機能性精神疾患における心理的機能に関する研究
統合失調症患者, 気分障害患者, 健常対照者を対象に合計2,700名から取得した認知機能障害やパーソナリティ特性等の既存データを解析し,これらの患者における心理的特徴およびそれに寄与する要因を明らかにする. 神経研究所疾病研究第三部との共同研究として実施している. (堀,小川)
北茨城の被災地住民を対象とする精神医学的コホート研究
東日本大震災後に北茨城市の被災地住民に対するメンタルケアおよび調査・検体解析研究を実施した.その際に取得された既存資料・試料を新たに解析することで,うつ病やPTSDの発症リスクに関わる環境要因や遺伝要因を明らかにし,バイオマーカーの探索を行う.筑波大学等との共同研究として実施している.(堀,小川,吉田)
思春期児童のインターネット不適切使用とメンタルヘルスの関連についての研究
東京都医学総合研究所とTokyo Teen Cohortを対象とした共同研究を行った.インターネット不適切使用とメンタルヘルスの関連を因果推論のフレームワークを用いて解析した.これらの結果はSchizophrenia Bulletin誌に発表した.(成田瑞)
地域住民の飲料摂取と抑うつの関連についての研究
国立がん研究センターとJPHC-NEXTコホートを対象とした共同研究を行った.飲料摂取と抑うつの関連を因果推論のフレームワークを用いて解析した.これらの結果はClinical Nutrition誌に発表した.(成田瑞,堀)
地域住民の生活形態と自殺の関連についての研究
国立がん研究センターとJPHCコホートを対象とした共同研究を行った.生活形態と自殺の関連を因果生存解析のフレームワークを用いて解析した.これらの結果はEpidemiology and Psychiatric Sciences誌に発表した.(成田瑞,堀)
COVID-19罹患に関連する差別体験と精神病症状の関連についての研究
公共政策部とオンラインサーベイを用いた研究を行った.COVID-19罹患に関連する差別体験と精神病症状の関連を因果推論のフレームワークを用いて解析した.これらの結果はSchizophrenia Research誌に発表した.(成田瑞)
心的外傷後ストレス障害に対するオンライン持続エクスポージャー療法の有効性検証:多施設ランダム化比較試験
ウェブ会議システムを利用してオンラインの持続エクスポージャー療法を行う介入群とかかりつけ医の通常治療を継続する対照群の2群のRCTである.遠隔地にトラウマ専門治療を提供し医療格差を是正し実装を進めることが本研究の構想である.3例のリクルートを終了した.(井野,藤内,中野,須賀,利重,田中,丹羽)
心的外傷後ストレス障害に対する睡眠中音エクスポージャーの実施可能性確認研究(PTSD睡眠中音刺激研究)
トラウマを想起させるテーラーメイドの音刺激を作成し,それを徐波睡眠中に聞かせる研究の実施可能性を検証する研究である.2024年1月に倫理審査を通過し,目標リクルート数の6名をリクルートした.現在介入中である.(井野,金,中野,島津,藤内,坂口,関場)
難民・移民のこころのケアを広める研究 —支援者のメンタルヘルス実態調査とトラウマインフォームドケア研修-
難民支援職を対象として支援環境とメンタルヘルスの状態の関連を調査し,また質的なインタビューによって支援体験がメンタルヘルスに与える影響を検討する.本研究ではトラウマインフォームドケアの研修を実施し,支援者支援も合わせて行っていく.(井野,堀,須田,中野,田中)
北里大学との共同研究:血中不飽和脂肪酸とPTSDとの関連の検討
北里大学病院救急外来に搬送された方々を対象に,入院時の血漿中脂肪酸組成と受傷後1/3ヶ月目時点でのPTSD判定やPTSD重症度スコアとの関連を検討した.受傷時の血中リノール酸などの特定の脂肪酸の濃度とその後のPTSD症状の判定や重症度との関連が明らかとなった.本研究の成果はNeuropsychopharmacology Reports誌に掲載された.(小川,成田瑞,堀,金)