
社会適応の簡便な測定法:動物名の想起順序のテキストマイニング解析による
統合失調症患者の評価
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP) 精神保健研究所児童・予防精神医学研究部 和田歩リサーチフェロー、住吉太幹部長は、NCNP病院精神リハビリテーション部 吉村直記部長、福島大学人間発達文化学類 住吉チカ教授らとの共同研究により、1分間に想起される動物名の順番についてテキストマイニング法1)を用いて解析することで、統合失調症患者の社会機能(日々の活動、労働能力、他人との関係維持など)を評価できる可能性を見出しました。
本研究成果は、日本時間2025年4月15日に「Schizophrenia」誌(Springer Nature社)に掲載されました。
ポイント
- 統合失調症患者の認知機能や社会機能の客観的評価は、診療や支援の計画立案に重要です。しかし、これらの測定には時間を要するため、日々の臨床場面への実装は容易ではありません。こうした中、統合失調症患者の社会機能を短時間で評価しうる簡易な方法を考案しました。
- 統合失調症の患者は脈絡のない言葉を発したり、発話する単語や話題が少なくなったりすることがあります。これらの症状は、社会機能に大きく影響することが知られています。
- 今回、認知機能を測定するカテゴリー流暢性課題(CFT)に着目し、テキストマイニング法を用いてデータを解析し、各々の患者における意味記憶2)を定量化しました。その結果、CFTにおける動物の名前を発話する順番に意味的なまとまりがあるほど、患者の社会機能が良好であることが、初めて示されました。
- CFTは実施に必要な時間が約1分間と短いため、今回の研究成果が日常診療での認知機能・社会機能評価を容易にし、統合失調症患者に対する、より適切な治療や支援の提供につながると期待されます。
研究の背景
統合失調症は、幻覚や妄想などの「陽性症状」、感情の平板化や意欲の低下などの「陰性症状」、および認知機能障害などの症状で特徴づけられる代表的な精神疾患です。適切に治療されない場合、他人とのコミュニケーション、日常生活機能、労働(家事を含む)などの「社会機能」が低下することが少なくありません。
統合失調症の認知機能障害の一部として、言語に関連する意味記憶の減弱が挙げられます。例えば、脈絡のない言葉を発したり、発話する単語や話題が少なくなったりすることがあります。これらの症状は、社会機能に大きく影響することが知られています。しかし、個人ごとの意味記憶の差異が社会機能にどう影響するかは、これまで直接的には調べられてきませんでした。
研究概要
本研究の目的は、(1)テキストマイニング技術を用いることで、個々の統合失調症患者における意味記憶を定量化すること、(2)意味記憶の減弱が社会機能低下に関連するかを統計的に示すことです。

意味記憶の測定には、統合失調症の認知機能障害を評価する、国内外で広く用いられているテストバッテリーにも取り入れられている「カテゴリー流暢性テスト(CFT)」を用いました。CFTは、参加者に1分間でできるだけ多くの動物の名前を口頭で回答してもらう簡易な検査です。
従来のCFTでは、回答した動物の数のみが評点されます。一方、今回の研究ではどの動物がどのような順序で回答されたかに注目した解析を行いました。具体的には、Word2vec3)という大規模言語モデルを用い、隣接する動物間の意味的な類似度を算出しました。これにより、回答した単語が同じ意味グループにどの程度まとまっているか(クラスタリング得点)や、異なる意味グループ間の切り替えがどの程度行われているか(スイッチング得点)といった、意味記憶の組織化の程度を数値化しました。
本研究の対象は、統合失調症早期患者139名(女性76名、男性63名)および健常対照者98名(女性40名、男性58名)で、両群とも平均年齢は約27歳前後、平均教育年数は約14年でした。社会機能の評価には、面接形式の評価尺度で国際標準とされるSLOF(Specific Levels of Functioning Scale)4)を用いました。SLOF日本語版の統合失調症患者の社会機能評価尺度としての信頼性・妥当性は、住吉ら*により検証されています。
結果として、統合失調症患者では健常対象者よりもクラスタリング得点が低いことが確認されました。また、クラスタリング得点とSLOF得点との間に有意な関連を認めました。一方、スイッチング得点と社会機能との間には、明確な関連は認められませんでした。以上より、CFTで動物の名前を発話する順番に意味的なまとまり(“イヌ、ネコ、ネズミ”、……、“ライオン、ゾウ、キリン”、……など)があるほど患者の社会機能が良好であることが示されました。
今後の展望
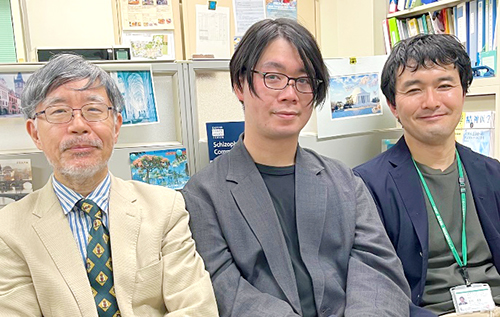
今回の研究成果により、短時間で得られるCFTデータをテキストマイニング法で定量化することで、統合失調症患者の日常生活の困難さの程度を簡便に測定しうることが示されました。今後、こうした認知機能評価法の臨床応用が進むことで、社会機能に着目した診療や支援の計画立案に役立つことが期待されます。
用語説明
1) テキストマイニング法:テキストを単語やフレーズなどの単位に分割し、それらの出現頻度や共起関係(同時出現)などを集計し、定量的に解析すること
2) 意味記憶: 事実や概念に関する知識を蓄えた記憶
3) word2vec: 単語を数値ベクトル(数値の並び)で表現する自然言語処理の手法。数値ベクトル同士の距離を測ることで、単語同士「意味の近さ」を定量化することができます。
4) SLOF(Specific Levels of Functioning Scale): 統合失調症患者の社会機能のための国際標準とされる評価尺度。面接方式で行われ、対人関係(他者との自発的な交流の頻度および質、社会との関わり)、活動(趣味や日常生活での自発的な行動の度合い)、労働技能(職場や作業環境での適応能力および集中力・持続力)を客観的に評価します。
原著論文
・論文名:Semantic memory disorganization linked to social functioning in patients with schizophrenia.
・著者名:Wada, A., Sumiyoshi, C., Yoshimura, N., Hashimoto, R., Matsumoto, J., Stickley, A., Yamada, Y., Kikuchi, A., Kubota, R., Matsui, M., Nakachi, K., Fujimaki, C., Adachi, L., Yamada, R., Sumiyoshi, T.
・https://doi.org/10.1038/s41537-025-00615-z
参考文献
*Sumiyoshi, T., et al. Cognitive insight and functional outcome in schizophrenia; a multi-center collaborative study with the specific level of functioning scale–Japanese version. Schizophrenia Research: Cognition 6, 9-14.
https://doi.org/10.1016/j.scog.2016.08.001
研究経費
本研究結果は、日本学術振興会および国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費の支援を受けて行われました。
<関連リンク>
>精神保健研究所
https://www.ncnp.go.jp/mental-health/index.php
精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部HP
https://www.ncnp.go.jp/nimh/yobou/




