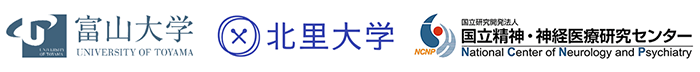
ネガティブな出来事における不確かな文脈記憶形成:
その神経生物学的メカニズムとうつ病の発症リスクとの関係を解明
―うつ病の予防・治療に役立つ可能性―
ポイント
- うつ病の発症リスクをもつ人では、ネガティブな出来事を経験したときに、その出来事の全体像(文脈情報)が正しく記憶されていない。
- こうした記憶形成の失敗は、ネガティブな情報に注意を惹き付けられているときの扁桃体と腹内側前頭前皮質(vmPFC)との間の機能結合 と関連している。
- 代表的なストレスホルモンであるコルチゾールが多く分泌されているほど、出来事に遭遇してから時間が経過した後に、その出来事が起きた一連の流れ(時間的文脈)を思い出せなくなる傾向がある。
- ネガティブな情報の存在下における文脈記憶の形成不全は、うつ病の発症・増悪に密接に関与する「自伝的記憶の過剰一般化」(自身が経験した出来事の文脈情報について曖昧にしか思い出せなくなる現象) を介して、うつ病の発症リスクを予測説明することを初めて発見した。
概要
富山大学(学術研究部医学系の袴田優子教授)、北里大学(医療衛生学部の田ヶ谷浩邦教授ほか)、および国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(精神保健研究所の堀弘明部長)等は共同で、うつ病の発症リスクをもつ人では、経験した出来事のなかにネガティブな事柄が含まれるときには出来事の全体像を正しく記憶していないこと、こうした不確かな記憶形成が扁桃体―vmPFC間の機能結合やコルチゾールの分泌量と結びついていること、さらに、より長期的な文脈記憶の想起困難である自伝的記憶の過剰一般化と繋がり、うつ病の発症リスクを高める可能性があることを世界で初めて明らかにしました。研究の背景
うつ病は、一般人口の約1/5の人々が生涯に一度は経験するといわれ、再発しやすく、患者さん自身の苦痛はもちろん大きな社会経済的損失を伴う精神障害です。しばしば自殺にも結びつき、治療および発症・再発予防が喫緊の課題となっています。うつ病の発症および再発には、自伝的記憶の過剰一般化と呼ばれる記憶現象が密接に関与することが指摘されています。また、うつ病では、扁桃体やvmPFCと呼ばれる気分・感情の生起や制御に関連する脳領域の機能不全や、ストレスホルモン・コルチゾールの分泌過多が報告されてきました。しかし、自伝的記憶の過剰一般化によって示されるような文脈記憶の想起困難が、どのように神経生物学的に生じるのかというメカニズムについては、これまで明らかではありませんでした。そこで本研究は、自伝的記憶の過剰一般化が生じる背景に、何か出来事を経験した際にネガティブな事柄に注意を惹きつけられてしまうために、それ以外の情報、すなわち出来事の全体的な文脈情報を正しく記憶できていないのではないかという仮説を立て、これを検証しました。さらに、こうした文脈記憶形成不全の神経生物学的機序として、扁桃体の神経結合やコルチゾールとどのように関係するのかについても調査しました。
研究の内容・成果
本研究は、富山大学、北里大学、国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、金沢大学、京都大学と共同で実施されました。本研究では、うつ病の発症リスクをもつ人を含む、合計120名の成人を対象としました。ネガティブな出来事の文脈記憶を測定するために、ネガティブ(またはニュートラル)な対人刺激がランダムに出現するマイクロイベントを呈示する実験課題を作成し、そこに同時存在していた視知覚・空間・時間文脈情報に対する記憶成績を測定しました(図a.)。文脈記憶課題成績とコルチゾール分泌量は、符号化 (記憶形成)時と24時間経過後に2回測定されました。自伝的記憶の過剰一般化は、自伝的記憶検査により測定しました。さらに当事者の意識を伴わずに生じるネガティブな刺激に対する選択的注意の検出段階を捉えるために、機能的磁気共鳴画像法(fMRI) を用いてネガティブな対人刺激による注意干渉課題中の扁桃体の機能結合も測定しました。これらの変数間の関係を統合的に調べるため、調整媒介解析を行いました。結果として、うつ病の発症リスクをもつ人では、そうでない人と比べて、ネガティブな(対ニュートラル)対人刺激が出現しているときの文脈情報(とくに視知覚詳細)を正しく符号化できていないことを見出しました(図b.)。この文脈符号化成績の低さは、ネガティブ(対ニュートラル)な対人刺激から注意干渉を受けているときの扁桃体―vmPFC間の機能結合の減弱と関連していました(図c.)。加えて、うつ病の発症リスクをもつ人では、そうでない人と比べて、24時間経過した後、ネガティブ(対ニュートラル)な対人刺激が出現した際の前後の時間文脈を詳しく思い出せず、またストレスホルモン・コルチゾールの総分泌量が多いほど、この時間文脈に対する想起成績が低下する傾向がみられました。



さらに、こうした文脈記憶の符号化の失敗は、自伝的記憶の過剰一般化を部分的に媒介して、うつ病の発症リスクの有無を予測説明することを見出しました(図d.)。なお扁桃体―vmPFC間の機能結合とコルチゾールを統合的に考慮した調整媒介解析では、統計的に有意差には至りませんでしたが、扁桃体―vmPFC間の機能結合が、文脈記憶課題における符号化成績の低下から自伝的記憶の過剰一般化へと至る経路を調整する傾向もみられ、今後のさらなる研究の必要性が示されました。

今後の展開
本研究の特色は、視知覚的な文脈情報の符号化困難が、自伝的記憶の過剰一般化を介して、うつ病の発症リスクを高めうることを世界で初めて示唆した点にあります。また、符号化の低下は、ネガティブ(対ニュートラル)な対人刺激による注意干渉中の扁桃体―vmPFCの機能結合の弱化と関連していたことから、出来事のなかに存在するネガティブな刺激に注意を惹きつけられることにより、全体的な文脈情報の符号化に失敗している可能性が示唆されました。コルチゾールは符号化成績低下には影響していませんでしたが24時間経過後の時間文脈の想起成績低下と関連しており、記憶の固定化 過程において遅延性効果を発動させる可能性が考えられ、今後のさらなる研究が期待されます。従来の心理治療では、ネガティブな出来事の記憶に苦しむ患者さんに対して、出来事全体に関する詳細な想起を促し、その意味づけ・解釈を再構築するようなアプローチが取られてきました。しかし、ネガティブな事柄を語ることはできても、その出来事が起きた全体的な文脈を「思い出せない」と訴える患者さんも少なからず存在し、従来のアプローチの適用が困難なケースもあります。今回の知見は、符号化段階で文脈記憶形成を促進することの重要性を示唆しており、こうした介入手法は従来の心理治療には反応しにくいうつ病に対する新たな治療および予防法の一つとなることが期待されます。
本知見は、精神神経内分泌学分野における伝統的な学術雑誌であるPsychoneuroendocrinologyに10月19日にオンライン掲載されました。
本研究は、日本学術振興会・科学研究費補助金(基盤B)および上原記念生命科学財団の研究助成金に基づき実施されました。
本研究に関連して申告すべき利益相反はありません。
論文詳細
論文名:Contextual memory bias in emotional events: neurobiological correlates and depression risk著者:Yuko Hakamata, Shinya Mizukami, Shuhei Izawa, Hiroaki Hori, Mie Matsui, Yoshiya Moriguchi, Takashi Hanakawa, Yusuke Inoue, Hirokuni Tagaya.
掲載誌:Psychoneuroendocrinology
DOI:10.1016/j.psyneuen.2024.107218
URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453024002634
用語解説
ⅰうつ病:一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、不眠や食欲低下、疲労感などの症状を伴い、日常生活に支障をきたす精神障害。ⅱ機能結合:時間軸上で共通して生じる脳活動の変化から推定される2つ以上の脳領域間の機能的な結びつきのパターン。
ⅲ自伝的記憶の過剰一般化:自伝的記憶の概括化/過度の一般化とも訳される。経験した出来事の文脈(いつ・どこといったような情報)を鮮明かつ具体的に思い出せなくなる現象。例えば、「昨日隣の佐藤さんと地区で行うバレーボール大会について話をした」といった、はっきりとした特定の出来事の記憶ではなく、「私は近所の人にいつも嫌味を言われる」といったように、具体性を欠くかたちで漠然と曖昧に出来事の記憶が思い出される現象をいう。複数のメタ解析により、うつ病の発症や増悪と密接に関連することが明らかにされている。
ⅳ符号化:記憶の基本的過程のひとつであり、情報を取り込んで記憶情報として保持されるまでの「憶える」過程をいう。
ⅴfMRI:磁気共鳴画像(MRI)装置を用いて、生体の脳や脊髄を一定時間連続的に撮像し、脳活動(神経活動とシナプス活動等の総和)と相関するMRI信号の変動を身体への侵襲なく計測する技術。
ⅵ固定化:新しい情報を学習した後、ごく短時間保持される記憶(短期記憶)から、長期にわたり安定的に保持される記憶(長期記憶)へと移行する過程。
参考リンク




